 寄席紳士録
寄席紳士録 五代目三遊亭新朝
五代目三遊亭新朝は明治から昭和にかけて活躍した落語家。関西の落語家・桂鯛助の息子に生まれ、早くから高座に出た。春風亭柳枝、三遊亭圓生と名手に師事をし、長い息を保ち、名跡を継いだものの、ブレイクすることはなかった。
 寄席紳士録
寄席紳士録 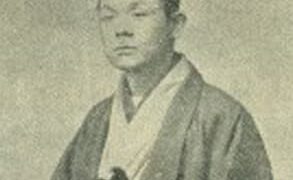 寄席紳士録
寄席紳士録 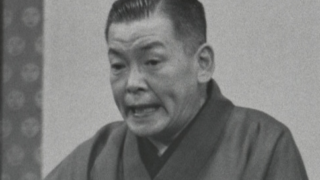 一門系図
一門系図  一門系図
一門系図  一門系図
一門系図 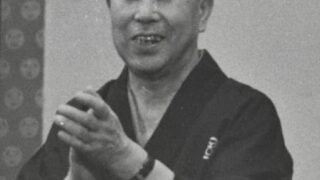 一門系図
一門系図 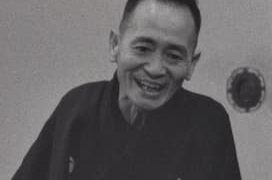 一門系図
一門系図 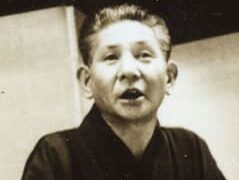 一門系図
一門系図  一門系図
一門系図 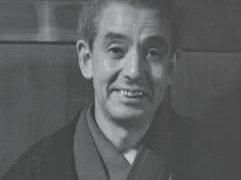 一門系図
一門系図