三遊亭金朝(三代目)
人 物
三遊亭 金朝(三代目)
・本 名 赤田 金太郎
・生没年 1877年?~1914年2月13日
・出身地 東京 下谷
・活躍年代 1890年代?~1914年頃
来 歴
父は二代目三遊亭金朝、弟は戦前歌舞伎鳴物の名人とうたわれた九代目田中伝左衛門。
幼いころから父の影響で寄席に出入りし、芸を仕込まれて育った。経歴は『名人名演落語全集 第9巻』の没年表に詳しい。
三遊亭金朝 ①大正3・2・13歿、35歳②赤田金太郎③台東区永久寺⑤金山諦道信士⑥四代目圓喬門下金喬、また圓慶と改め、四代目左楽門下で枝太郎と改名、さらに金朝を襲ぐ。二代目金朝の実子。
弟の田中伝左衛門が「下谷数寄屋町」の出身を自称したため、当人もここの生まれだろう。
明治20年代に橘家圓喬に入門し、「橘家金喬」。後に三遊亭圓遊門下へ移籍して「三遊亭圓慶」。さらに「三遊亭遊人」と名乗っている。
1900年7月、三遊亭圓遊と寄席組合が喧嘩をはじめ、圓遊は独断で自身と一門の出演を差し止めた。これに動揺した遊人は三遊亭花圓遊などと語り合い、師匠に名前を返して三遊派を脱退。柳派へ移籍した――と『明治の演芸6』にある。
同年、四代目柳亭左楽の門人になり「三代目柳家枝太郎」を襲名。後に寄席と圓遊一門が和解したため、柳派を去り、三遊派に復帰している。
1902年、三遊亭金朝を襲名。『万朝報』(1909年3月25日号)の金朝の訃報に「明治三十五年、息子に名前を譲った」という旨がある。
その後は三遊派の中堅として活躍したが、そこまで売り出すことはなかった。ただし、「面白い噺を面白くなさそうに話す」という芸に優れていたようである。
1907年発表の森曉紅『芸壇三百人評』の中で――
百五十八 三遊亭金朝
随分秀れて不器用な話、笑い話をおかしくなく話す處が餘人に出來無い處、素話一方が呆れたもの也、おやぢは故高島屋の聲色で賣つたもんだから、君も新左團次の聲色でも研究してやつて見ちやアどうだィ、何に馬鹿にしなさんな、そんなんぢゃァ無いつてナール程。
明治末に肺を病んで体調を崩し、寄席から退いて、赤坂にあった寄席を買い取り、赤坂豊川亭として経営していた。その席亭になったのも間もなく肺病をこじらせて亡くなった。
子供をそのまま大きくしたような人間だったらしく、家督から親の面倒まで全部弟に見させていたという、ある意味では身内に恵まれた人物であった。
甥っ子の十代目田中伝左衛門の聞書き『囃子とともに』に――
とうとううだつが上がらず、弟の先代伝左衛門に世話になりっぱなしだった。親の死に水まで弟にとらせてのんびり一生を送り、自分には長男としての自覚も、悩みもなかった。そこでみずから「三遊亭金朝無悩居士」としたのはおもしろい。


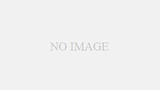
コメント