三遊亭金遊斎
人 物
三遊亭 金遊斎(三代目)
・本 名 山本 菊次郎
・生没年 1850年9月20日~1917年9月8日
・出身地 江戸?
・活躍年代 1870年代?~1917年
来 歴
三遊亭金遊斎は明治から大正初期まで活躍した芸人。若い頃から落語よりも珍芸が得意で、操り人形を十八番にした事から「あやつりの金遊斎」と称された。経歴らしい経歴は『名人名演落語全集 第9巻』の没年表に詳しい。
三遊亭金遊斎……①大正 6 ・ 9 ・ 8 歿、66歳②山本菊次郎③嘉永3・9・20④六代目文治門下文六または文生、また文八と改め、小圓遊門下となり小二三、または小遊太と改める。のちに二代目金馬門下金遊斎と改名。”あやつり獅子”を得意とした。
明治初年に名人と称された六代目桂文治に入門しデビュー。桂文六、桂文生と転々としたが、なかなかうまくいかなかったという。
明治中頃に初代三遊亭小圓遊門下へおさまり、「小二三」。後に三遊亭小遊太と改名して、一枚看板を掲げる。
1902年に師匠・小圓遊が亡くなってからは旅回りを多くしていた二代目三遊亭金馬に見出され、彼と行動を共にするようになる。
1900年代にはすでに「写し絵」「珍芸」といった部類を得意としていたようであり、既に一枚看板で「写し絵・小遊太」などと出ている。中でも獅子舞の人形を用いた「あやつり」は絶品だったそうで、落語よりもその芸で売れてしまったという。
1909年頃に金馬門下に入り、「金遊斎」と改名。師匠に同行して地方巡業で暮らしていたという。
1910年夏には師匠や弟弟子の金登喜(柳家金語楼)と共に朝鮮・満州を巡業。『満洲日日新聞』(1910年7月26日号)に――
●花月席の落語 久し振りに變つたものを出した花月席は三遊亭金馬一座が神田囃しの町廻りに景氣附き席も柱を廻いたり疊を替えたり面目を一新して居るさて一座は金馬が軽妙な落語に花堂の尺八龜治郎の曲藝しんみりしたものでは花圓遊の人情話しなんどしつきりなしに肩の凝らない面白味澤山前座からの金平、金遊齋、小つま、市馬などとり〳〵に笑はせた上に當年九歳の金登喜と云ふが現はれて俗謠盡しの義太夫を前藝と仕り松づくしの手踊となるこれが可愛らしく綺麗でお後は花圓遊の人情ばなし跋の花圓遊と云へば大低お馴染の筈亀次郎の曲藝で眼先きがかはり花堂得意の尺八は義太夫のさはりを合奏で聴かせるお好みの附錄も二つ三つ揚騰に遊ばせて金馬の落語一々事新しく吹聴するにも及ぶまい上方風のくさくない所は満洲でのお初もの七十五日はいざ知らす一晚交けの命は延びさうだ……
子供の頃同座した柳家金語楼によると「鞠を作るのが趣味であった」という。柳家金語楼『話のジェスチャー』の中に――
むかしの落語家には変わり者が多かった。三遊亭小遊太という老人は、地方巡業のときには給料をもらうと、真綿を買い込んで真綿で糸を作って大きなマリをいくつもいくつもこしらえる。糸といっても二本の指でコヨリのようにやるので、細いとこもあれば太いとこもある。三年間の巡業で真綿のマリが十七できた。
これに仕立寸法を書いて、染色も記して、知人の織元へ送った。それから半年ほどたってから、織元から送ってきたので、自分で作った着物だと、大自慢で東京で着ていたが、どうも人間が着る着物の地としては、分厚でかたすぎると思ってたら、手首や襟元がキズだらけになっている。柔道着にのりをつけたような、手首も首筋も着物に、こすられて赤肌になってるので誰だったか”その着物はやめたほうがいいよ”というと、小遊太は情けなさそうな声で”四年がかりで作った着物を、たった四日でやめられますかい”って、泣きだしそうな顔でいったとき、手品師の帰天斉小正一という人が”私のモーニングのカラーをやるから、じゅばんに縫いつけたまえ、ああ手首もか、じゃワイシャツもやろう、明日家へとりにきたまえ”という。
小正一は冗談でいったつもりだったが、小遊太は懸命なので、翌朝ワイシャツとカラーをもらって帰り、じゅばんの襟にカラーを縫いつけ、袖のところへカフスを切って縫いつけて、ニコニコ顔で楽屋へ現われた”お蔭で痛くなくなって、いい気持ちですよ”といったが、やがて困ったような顔をして”電車のなかでみんなジロジロ見て、少し気まりが悪かったが”という。そりゃジロジロ見るはずで、コチコチ着物にカラーつき、袖口からカフスボタンがチラチラ見える、どうみたって変に決まっている。しかし小遊太も立派な奇人のひとりであった。数か月間その姿で往来をしていた。今の人は金をやっても”気ちがいじゃあるまいし”と断わるでしょう。私も子供心に一緒には電車へ乗れなかった。
とバカバカしい話が出ている。
最終的には中央の高座には戻らず、金馬一座で活躍したまま年を取り、そのまま亡くなったという。



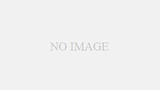
コメント