春風亭盛枝(岡本貞次郎)
人 物
春風亭 盛枝
・本 名 岡本 貞次郎
・生没年 1864年10月22日~1912年5月14日
・出身地 江戸 新堀端
・活躍年代 1870年代?~1897年頃
来 歴
春風亭盛枝は明治期に活躍した芸人。伊藤燕旭堂という講談師、母は女義太夫の芸人、弟・梅三郎は講談師で「清草舎英昌」という芸人一族に生まれ、当人は落語家を志したが、後に新派俳優となった。
経歴らしいものは『名人名演落語全集 第9巻』に出ている。
元春風亭盛枝……①明治45・5・14歿、49歳②岡本貞次郎③元治元・10・22④小勝門下小吉、のちに三升家勝蔵から春風亭盛枝と改名、さらに岡本貞次郎の芸名で舞台に上った。講釈師伊東燕旭堂(岡本栄次郎)の実子。
父は伊藤燕旭堂という講談師、母は女義太夫の芸人、弟・梅三郎は講談師で「清草舎英昌」と名乗った芸人一家の生まれ。
親父は元々士族であったというが、いい待遇を得られない事と講談好きであったことから講談師となり、そのまま講談の道に飛び込んだという変わり種であった。
中根喜三郎・海老名香葉子兄妹の親父で、東京大空襲で亡くなった中根音吉の随筆集『竿忠の寝言』によると、中根忠吉とは寺子屋の同窓生であったという。
此燕旭堂の枠が岡本貞次郎と云ふ新派の俳優で、淺草公園なぞで一頃人気も相當あった男、此人は忠吉の寺子屋友達であった、此母、つまり蒸旭堂の女房は、義太夫の師匠をして居った。岡本貞次郎の舎弟が、親父と同じ講談師と成って、之が現在の清草舎英昌だ。
父母に連れられて幼い頃から芸能界に出入りし、幼くして三代目三升亭小勝に入門することとなった。前座名は三升亭小吉という。
父は売れっ子講談師であった一方、高座で変なことを口走る癖があり、これがために何度も警察に拘引されるという問題児であった。「今の政府は柳原の大道易者だ、算木(参議)をおいて、筮竹(税)をとる」などと放言し捕まっている。
後に一人前となり、「三升家勝蔵」を襲名。若手として高座に出ていたというが、間もなく柳派に移り、「春風亭盛枝」と改名している。
落語家としての評判はそこまで伝わらず、当時の番付などを見ても若手扱いのままで止まっている。一方、血筋と師弟関係の筋目の良さもあり、落語家芝居などでは相応の役を貰っている。
1896年頃に落語家を廃業し、当時売り出しの新派俳優の伊井蓉峰に入門。本名で舞台に出るようになった。
初舞台は1897年1月1日より開催の、赤坂演技座『探偵実話山田実玄』『吉富組』だろうか。常磐津文字若、水溜九郎兵衛、行列組なる役を務めている。
その後は伊井一座の敵役・女方として活躍。女方は得意だったと見えて、若い娘から年増までいろいろと演じている。
敵役としては新作もこなしたほか、伊井演じる寺子屋の松王丸に対し、春藤玄蕃を演じるなど相応の格式はあった模様。
久保田万太郎は『三筋町より』なる随筆集の中で、その印象を記している。
岡本貞次郎は、うすあばたのある、三尺ものゝ巧い役者だった。この役者、後に、獎勵會といふものが解散してから、暫くして、そのころはやりかけた活動寫真のなかに入り、實物應用といふものをはじめた。わたしの記憶にもしあやまりがなかつたならば、役者にして、活動小屋に関係を持つたそれがそも〳〵の人間だった。
1910年頃に伊井一座を脱退し、独立して「岡本貞次郎一座」を結成。浅草の美音館という劇場に出入りし、喜劇と新派を演じるようになった。
この頃、美音館が映画興行をやっていたこともあり、映画と実演を組み合わせた「連鎖劇」なる芝居を率先して演じ、連鎖劇ブームの一翼を担った。
芸も人気も大成する矢先の1912年5月、48歳の若さで死去。
弟の梅三郎は「清草舎英昌」を襲名し、寄席の世界で名人上手として名を残し、80近い天寿を全うしたのを考えると夭折の部類である。


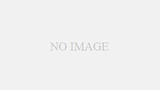

コメント