横目家助平(初代)
人 物
横目家 助平
・本 名 利倉 常次郎
・生没年 1862年2月~??
・出身地 ??
・活躍年代 明治10年代?~昭和初期
来 歴
横目家助平は明治初頭から昭和にかけて活躍した落語家。「助平」という凄まじい芸名の通り、愛嬌を前面に押し出した不思議な人柄で名前を残したという。
経歴には謎が多いが、明治初頭に晩年の二代目古今亭志ん生に入門。「古今亭志ん吉」と名乗る。
1889年に師匠と死に別れ、兄弟子の雷門助六(三代目志ん生)門下へ移籍。
1896年、正式に「雷門助平」と名乗る。その名前の通り、芸のうまさよりも愛嬌とバカバカしさを前面に押し出したという。
1907年に発表された森曉紅『芸壇三百人評』の中に――
七十五 雷門助平 此麼男に対して、旨いまづいは別問題だ、唯延とのんき珍な面と、真に苦勞の無さ相な呑気な調子とを以て、僕は面白がッてやる。
明治末(40年代)に「横目家助平」と改名。「横目を使う助平」とは振るっている。
高座では『お芋の説教』『女中志願』『お半長右ヱ門』『源平』などが十八番であったといい、今日の漫談に近いような雑話や顔芸を生かした噺も十八番であったという。
大正年間には愛嬌者として有名だったそうで、珍顔と珍芸で売った。『世の中』(1917年1月号)掲載の「当世愛嬌者番付」なる記事の中に、「行司」として生方敏郎・生田長江と並んで横目家助平が出ている。
愛嬌者だけに愛嬌のある話題も多い。小島貞二編纂の『落語名作全集 別巻』の逸話集に以下のような話が出ている。
目がロンドン・パリで、落語家以外考えられないような珍フェースで、声がまた奇声。はなしも陽気で、歌もうまかった。このひとのオハコは『お妾のお目見得』という、いまの『女中志願』のような落語。妻君に子僕がないところから、妻君公認の第二号を募集する。その口答試問のバカバカしさがミソだが、これをやるときの目をグルグル回す顔の表情など、まさに珍無類だったという。
あるとき、滑稽講談をやっていて、切れ場にこまった。
「たばこを吸っているとその鼻先へ、ポタリと落ちたものがある。何事ならんと、手をさしのべてみると、スルリとしたもの。電気をつけてみておどろいた。天井からしたたり落ちた血汐のしずく。あわてて二階にかけ上がり、ここに一個の死体を発見し、警察へかけこむという一条……明晩への、読み続きといたします」 と切る。さて、明晩はどう発展するのだろうと、客がききに来る。助平は、おもむろに、せきばらい一つ、 「昨晩、伺いかけに相なっておりますところの、天井から血汐の一件……なあに、おどろくこたありません。猫がとったとみえて、一匹のねずみの死、これを交番にとどけて五銭になった……」
客は怒るより、あきれて吹き出した。アドリブもかなりきいたことがわかる。
また、1957年に毎日新聞が出した『横浜今昔』の中に、横浜の寄席で助平が猿芝居の猿に惚れられた話が出ている。
ちょうど境内でサル芝居がかかっていて黒山の人だかり、 落語家一行も人々にまじってのぞき見していたまではよかっこと、横目家助平さんという話し家のどこが気にいったのか踊っていたサル君がするすると近よって来て助平さんが着ていた立派な紋つき羽織にとびつき、びりびりとばかり破いてしまった。驚いた助平さん、はっとして退参におよんだが間に合わない。同夜は仕方なく羽織なしで高座をつとめました。するとなんと楽屋に「染代」として無名で金二円なりが送られてきた。
話し家一同が助平さんを囲んで『だれか心当りあるか」とたずねたところそんな人とてないということで、 一同よくよく考えたところ昼間の一件を見ていたお客さんのひとりが“おかわいそうに”とばかりそっと届けてくれたものとわかって一同芸人に対するその細かい心づかいにおおいに感激した次第。
奇行も多く、「自分の入れ歯の調子がいいというのを喜んで、愛犬を総入れ歯にした」「庭がないのに石灯籠を買って来た。置く場所がないので畳を一枚あげ、床を抜いてそこに置いた」など逸話が残る。
一方、愛嬌者がゆえに文人や演芸関係者の評価は意外に高い。
社会主義者の荒畑寒村は『寒村茶話』の中で――
むかし二つ目に横目屋助平っていう妙な名の噺家がいましてね。芸名からして、もとよりうまいはずはない。ところがこの芸人の十八番で、他の追随を許さない出し物が一つあってね、例の「踊る平家は久しからず」っていうサゲの『源平盛衰記』なんですよ。この話も近ごろはあまりやりませんが、つい先ごろ林家三平がテレビで出しました。こりゃ珍しいと思って拝観謹聴したんですが、まあ芸が拙いの、話が下手のっていう段じゃなくて、 その高座行儀の悪さ加減に、ぼくはもう憤慨の沖を通り越して、ただただ驚き呆れるばかりでしたよ。
詩人の金子光晴は晩年の随筆集『ほりだしもの めでたき御代のおはなし』の中で――
もう一人は、横目家助平という裂相の巾着爺いで、これは一人二役でせりふの受わたしをする。油でかためた高齢より、つぶし島田にゆいたいねがい、などとへんなしなをしていうせりふに、ぷつとふき出さずにはいられないおかしみがあった。
と記している。
長らく柳派に所属していたが、1917年の演芸会社・睦会の分裂騒動では柳派の残党である睦会に参加。そのまま関東大震災前後まで同会に所属していた。
晩年まで大看板になり切れず、愛嬌を振りまきながら余生を送ったという。
1927年に正岡容が発表した『明治漫談紅毛人メガネ』なる随筆集に「助平の死」というタイトルがある。この頃には没していた模様か。



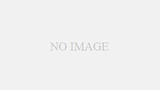
コメント